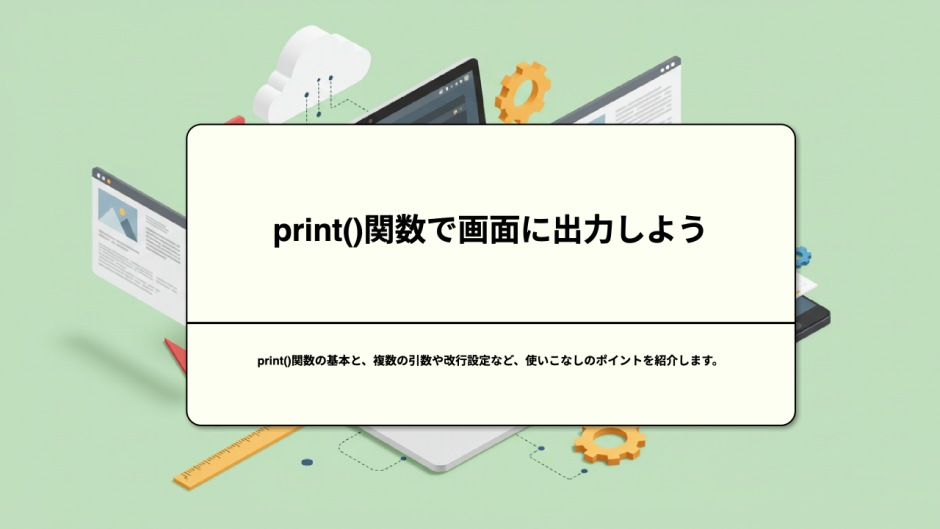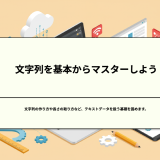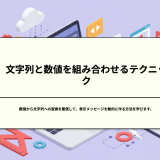print()関数で画面に出力しよう
Pythonでプログラムの動作を確認したいときや、処理途中の変数をチェックしたいときに最もよく使われるのが、print()関数です。この記事では、print()関数の基本的な使い方から、複数の引数を扱う方法、改行や区切り文字の指定など、初心者の方でも理解しやすいように丁寧に解説します。実際にサンプルコードを動かしながら、出力結果を確認しつつ学んでみましょう。
print()関数の基本
まずは、print()関数の最も基本的な使い方です。Pythonでは、print()関数に文字列や数値などを渡すだけで、画面に出力できます。例えば次のように記述します。
print("Hello, Python!")
このコードを実行すると、ターミナルやコンソール上に Hello, Python! と表示されます。print()関数の引数に文字列を指定する場合は、ダブルクォートまたはシングルクォートで囲みます。数値を出力する場合は、クォートで囲まずにそのまま記述してもOKです。
print(123)
上記のコードを実行すると、画面には数字の123が表示されます。このように、print()は最も手軽に結果を確認するための方法として重宝します。
複数の引数を指定する
print()関数には、カンマ区切りで複数の引数を渡すことも可能です。例えば次のサンプルを見てみましょう。
name = "Alice"
age = 20
print("Name:", name, "Age:", age)
実行結果は下記のようになります。
Name: Alice Age: 20
print()関数では、複数の引数を指定したとき、デフォルトでは半角スペースで区切って出力されます。これはsepパラメータによって制御されており、後述する方法で変更することもできます。
改行を制御する: endパラメータ
print()関数はデフォルトで、出力の最後に改行文字(\n)を付与して出力を終了します。しかし、改行せずに表示を続けたい場合や、他の文字で終わらせたい場合は、endパラメータを指定します。
# デフォルトの例(改行あり)
print("Hello")
print("World")
# endパラメータを変更して改行を抑制
print("Hello", end="")
print("World")
上記のコードを実行すると、前半は改行が入るため
Hello
World
と出力され、後半ではend=""により改行が入らず、
HelloWorld
と一行で表示されます。endには文字列を指定できますので、例えばend=" "(半角スペース)を使えば、次の出力との間にスペースが入ります。
区切り文字を変更する: sepパラメータ
先ほど説明したように、print()関数で複数の引数を指定した場合、その間はデフォルトでは半角スペースで区切られます。もしカンマやハイフン、他の区切り文字を使いたい場合は、sepパラメータを利用します。
print("apple", "banana", "orange", sep=",")
print("apple", "banana", "orange", sep=" - ")
実行結果は以下のようになります。
apple,banana,orange
apple - banana - orange
このように、状況に応じて区切り文字をカスタマイズできると、ログを整形したり、CSV形式のデータを出力したりするときに便利です。
文字列を組み合わせるいくつかの方法
文字列を出力する際は、+演算子で連結したり、format()メソッドやf-stringを使って読みやすく構成したりすることもできます。例えば、f-stringを用いた場合は下記のように記述できます。
name = "Bob"
age = 25
print(f"Name: {name}, Age: {age}")
この例では、nameとage変数の値を波括弧{}で囲んで埋め込むことで、簡潔かつ可読性の高い形で出力できるのが特長です。複数の値を扱うときは、format()メソッドと合わせて、用途やチームのコーディング規約に応じて使い分けましょう。
print()関数を使いこなすポイント
- デバッグ用にprint()を活用する
コードの動作確認で最も手軽なのがprint()関数による値の確認です。エラーが出たときや、意図しない挙動をするときは、一時的にprint()で変数の中身を出力してみると良いでしょう。 - 制御構文と組み合わせる
forループやif文などと組み合わせて、処理過程でどのように値が変化するかをこまめに出力すると、バグやエラーを素早く発見できます。 - 出力を一時的に停止するとき
コードの中で大量にprint()を使うと、ログが増えすぎることがあります。その場合はコメントアウトするか、条件付きでprint()を行う処理を組むなどして、必要な部分だけを表示する工夫をするとよいでしょう。
まとめ
この記事では、Pythonのprint()関数の基本的な使い方から、複数引数の指定、endパラメータによる改行制御、sepパラメータによる区切り文字の変更などを解説しました。print()は最もシンプルな出力方法である一方、少し工夫するだけで出力を整理しやすくなり、デバッグを効率化するのにも役立ちます。
初心者の方はまずはprint()関数を自由に使いこなせるようになると、コードの動作を理解しやすくなります。ぜひさまざまな出力パターンを試してみて、print()関数ならではの柔軟性を体験してみてください。